TOPへ
相続・遺言
相続手続き
Inheritance procedures
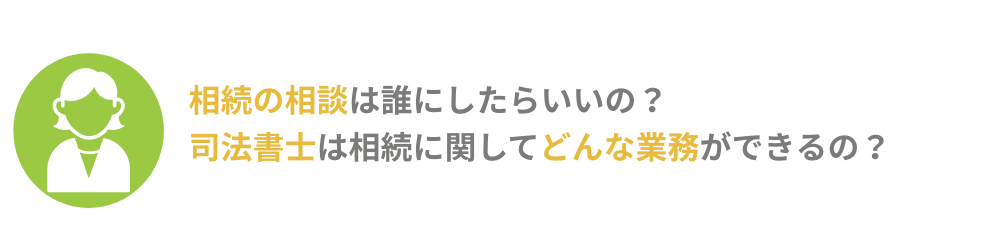
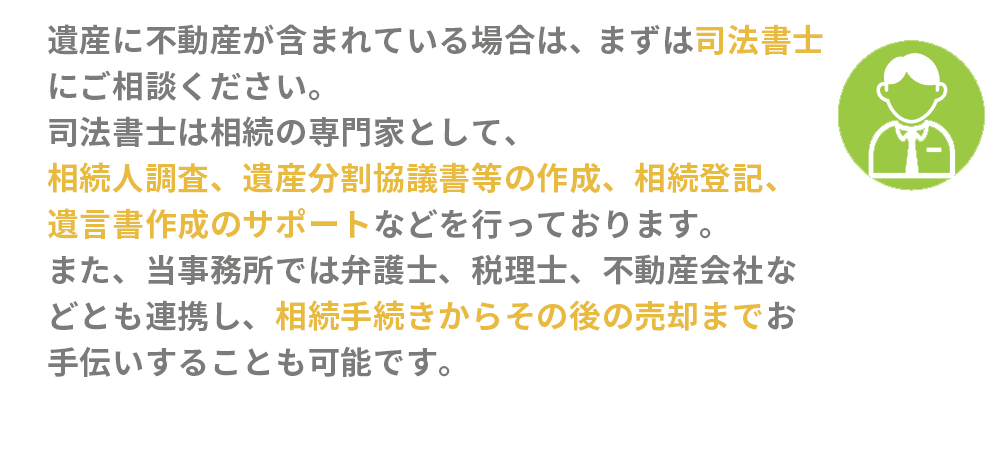
相続に関する調査
相続人・相続財産(不動産)の調査
相続人の調査は、お亡くなりになった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて調べます。
相続人調査の過程で思わぬ相続人が見つかることや、相続人が亡くなっており、そのお子様が相続人になるなどして、縁の薄い方が相続人として権利を主張してくる可能性があります。相続人である以上、たとえその相続分がわずかであっても、その方の同意なしに不動産等を処分することはできません。
相続財産(不動産)の調査では権利証や登記事項証明書、公図、名寄せ帳等から探していくことになります。
地方にご実家があるような方では、少し離れた裏山に山林を所有していることや、井戸のある土地を共有で権利を持っていらっしゃることもあります。
相続人と不動産の調査は並行して進めますが、戸籍を郵送で取得することもあるため、数週間から場合によっては数カ月かかることもあります。
遺産分割協議
相続人と相続財産が確定したら遺産分割協議を行います。
誰がその不動産を相続するのか、不動産をもらわない相続人には金銭を分けるのか、それとも不動産を売却して金銭を分割するのか等、どのように遺産を分けるのかを相続人で話し合います。
相続人の意見がまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続人が署名して実印で押印します。この協議書は相続登記の際に必要となります。
なお、遺言書があった場合でも、相続人全員の同意があれば遺言書と異なった財産の分け方をすることが出来ます。
相続登記
不動産の名義変更の登記は、その不動産を管轄する法務局に提出します。
現在ではインターネットを使ったオンライン申請により、司法書士は事務所のパソコンから日本全国の不動産の登記申請をすることが可能となりました。
2024年4月から、不動産を相続で取得したことを知ったときから3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になりました(過料の罰則あり)。
義務化より前に発生した相続に関しても対象です。
法務局に相続人代表者を届け出る「相続人申告登記」制度が設けられましたので、遺産分割協議が整わない場合は、この登記をしておくと、遺産分割協議が整うまでは罰則が科されないことになります。
相続放棄
相続放棄とはすべての相続財産(プラスの財産、マイナスの財産)を放棄することをいいます。お亡くなりになった方が多額の借金をしていた場合、相続人はその借金まで相続してしまいます。
マイナスの財産がプラスの財産よりも多かったとき、相続放棄の手続きをすることで、借金を相続することを避けることができます。
相続放棄は期限内に家庭裁判所に対して申し立てをする必要がありますので、注意が必要です。
遺留分・寄与分
遺留分とは「相続人が必ず相続できる遺産の割合」のことをいいます。
遺言書の内容で「すべての財産を一人だけに相続させる場合」や「自分にだけ遺産が遺されていなかった場合」にも遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をすることで、兄弟姉妹以外の相続人は一定割合の遺産を受け取ることができます。
寄与分とは、亡くなった方の財産の維持または増加に貢献した場合や病気や認知症の介護をしていた場合等に、
ほかの相続人よりも多くの財産を相続できる制度です。
寄与分をどのくらいにするかは相続人の協議によって決まります。
相続手続きスケジュール
Schedule
![相続発生 -[遺言書の有無確認][相続財産調査]](assets/img/will_cont03_img_01.png)
![7日以内 -[死亡届の提出]](assets/img/will_cont03_img_02.png)
![3ヶ月以内 -[相続放棄の申請][限定承認の申請]](assets/img/will_cont03_img_03.png)
![4ヶ月以内 -[準確定申告]](assets/img/will_cont03_img_04.png)
![10ヶ月以内 -[遺産分割協議書の作成、相続税申告・納付]](assets/img/will_cont03_img_05_2025-10.png)
![1年以内 -[遺留分侵害額請求]](assets/img/will_cont03_img_06_2025-10.png)
![できるだけ早めに行なった方が良いこと -[不動産登記(3年以内)、その他名義変更][生命保険の受取り、銀行口座解約 等]](assets/img/will_cont03_img_07_2025-10.png)
![相続発生 -[遺言書の有無確認][相続財産調査]](assets/img/will_cont03_img_sp_01.png)
![7日以内 -[死亡届の提出]](assets/img/will_cont03_img_sp_02.png)
![3ヶ月以内 -[相続放棄の申請][限定承認の申請]](assets/img/will_cont03_img_sp_03.png)
![4ヶ月以内 -[準確定申告]](assets/img/will_cont03_img_sp_04.png)
![10ヶ月以内 -[遺産分割協議書の作成、相続税申告・納付]](assets/img/will_cont03_img_sp_05_2025-10.png)
![1年以内 -[遺留分侵害額請求]](assets/img/will_cont03_img_sp_06_2025-10.png)
![できるだけ早めに行なった方が良いこと -[不動産登記(3年以内)、その他名義変更][生命保険の受取り、銀行口座解約 等]](assets/img/will_cont03_img_sp_07_2025-10.png)
よくある質問
Questions
Q1 相続についてどのような手続きを行ってもらえるの?

Q2 不動産の名義変更手続きにかかる期間は?

Q3 相続する不動産が地方にあります。現地で依頼した方が良いですか?

遺言書
Will
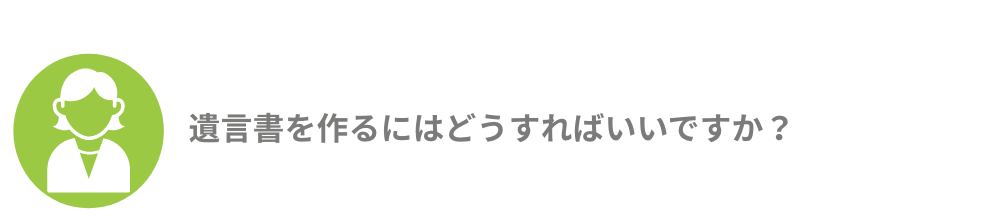
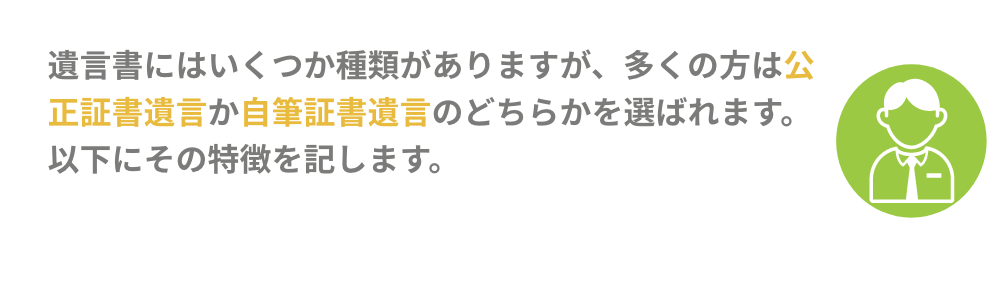
公正証書遺言
メリット
-
公正証書遺言は公証人がその作成に関与するため信頼性が高く、原本を公証役場に保管するため紛失や改ざんの心配もありません。
遺言者が亡くなったあとはそのまま各種手続きに使えるため、遺言者の希望をより早く実現することが可能です。
デメリット
-
作成の際に財産に応じた費用がかかります。
とはいえ、自筆証書遺言を作成し相続人間で争いが起きた場合、その解決にかかる時間と費用を考えると公正証書で作成するメリットがお分かりいただけると思います。
自筆証書遺言
メリット
-
ペンと紙があればいつでも作成することができ、費用もかかりません。
デメリット
-
民法に定められた要件を満たさなければなりません。
また、せっかく書いても、遺言者の死後にその存在自体を知られずに遺産分割協議がされてしまう可能性や、ほかの相続人から遺言書の無効を争われる可能性もあります。
さらに、遺言者の死後は家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。検認の手続きは、日時を指定し家庭裁判所で相続人を集めて行われるため、遺言書に従って財産を分けるまでには多少の時間がかかります。
検認手続は遺言書が本物であるという事を裁判所が確認するのではなく、遺言書の存在を確認するものです。このため、検認後に遺言書が本物であるかどうかが争われる可能性は残ります。※2020年7月から法務局で遺言書を預かる制度が開始しました。この保管制度を使うことで、内容の不備による無効や紛失等のリスクが減らせるほか、検認手続きが不要となり、速やかに預金解約などの手続きに使うことができます。
よくある質問
Questions
Q1 遺言書を作る際の注意点は?

Q2 遺言書は一度作ればいいの?

Q3 完璧な遺言書はない!?


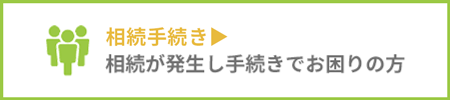

![[実家のたたみ方®]バナー](./assets/img/bnr-despo.jpg)